食育 一覧
イオン飲料(スポーツドリンク)は 虫歯菌の大好物
こんばんは。
熊本市中央区国府の 家族で通える歯科医院 ひかる歯科ちえこども歯科の甲斐田です。
イオン飲料は 体に良いと思って 与えているご家庭が多いのですが、 通常の水分摂取で イオン飲料を 頻回に飲むと
虫歯になってしまいます。
水筒にイオン飲料を入れて持って行っていたら虫歯になった、イオン飲料が大好きになってはまったら虫歯になった。
今まで虫歯がなかったのに 中学校で部活のときに イオン飲料を飲んでいたら 虫歯になった・・・
イオン飲料が原因の虫歯は 数えきれないほど 見てきました。
イオン飲料はジュースだと思って、飲んでいただくと良いと思います。
日本小児歯科学会のイオン飲料に関する 見解 は こちらです。
以下 小児歯科学会 ホームページより 抜粋
1) 乳幼児に対して:
* 過激な運動や極端に汗をかいたとき以外は,普通の水を与える。
* イオン飲料を水の代わりに使用しない。
* 下痢や嘔吐でイオン飲料を飲ませたときは症状が軽快したら中止する。のどが渇いたときは普通の水を飲ませるようにする。
* 寝る前や寝ながらイオン飲料を与えないようにする。夜中にのどが渇いたときには水を与える。
* 入浴後は水を飲ませる。
* 寝る前に歯を磨く。やむを得ず,寝る前や寝ながら与えるときは水を飲ませる。あるいは,与えた後に綿棒や指先にガーゼを巻き口腔内を清拭する。
2) 学童に対して:
* 運動で汗をかくときはイオン飲料を薄めて飲み,運動が終わったら,普通の水を飲む。
* イオン飲料のペットボトルを持ち歩きいつも飲む習慣や,食事をしながらイオン飲料を飲む習慣を付けないようにする。
* のどが渇いたときは水を飲む。
参考資料
イオン飲料とむし歯に関する考え方.小児科と小児歯科の検討委員会(平成16年1月16日)
2020年8月30日 | カテゴリー:新着情報, お母さん達からよくいただく質問, 食育 |
離乳食の食べさせ方について

こんにちは。
熊本市中央区国府の 家族で通える歯科医院 ひかる歯科ちえこども歯科の甲斐田です。
離乳食の食べさせ方について こうやって すすめると こどもの食べる機能が正しく身に付きやすい、というコツがあります。
そのことについて 以前より学ぶようになり、私より先を行く沢山の方々から学ばせていただいています。
その中のおひとりに こどもの発達について すごく学ばれている 香川県の 歯科衛生士さんがいます。
三木えりかさんという方です。
香川で ははこと というとっても素敵な教室をされています。
この ははこと の ホームページから お母さん向けの離乳食セミナー動画を購入することができるようになりました。
三木さんのセミナーは さまざまな 医療専門職の方にも大人気です。お母さん向けということで より分かりやすくなっていると思います。
離乳食をどうやって食べさせたらいいのかな?コツはあるのかな? と疑問に 思ったとき、ぜひオンラインでこちらの動画をご覧になるとすごく為になると思います。
私も購入して学ぶ予定です。今回はお母さん向けの とっても為になる離乳食セミナー動画のご紹介でした。
動画までは、という方は ブログもとても勉強になりますので、ぜひ読んでみてくださいね。
2020年7月13日 | カテゴリー:新着情報, お母さん達からよくいただく質問, こどもの 口腔機能を 育てるには, 食育, その他 |
お子さんへの おやつ教育

先日、ある歯医者さんが書いた本を読みました。
基本的に 歯科治療はしなくてよい、という内容のものです
虫歯は生活習慣病ですから、食生活をただせばよくなる、というのはその通りだと思います。
患者さんに食生活についてのお話はしていますが、実際にはそれ程簡単ではないようです
虫歯の治療をする→その後しばらく来院されず→1年後また新しい虫歯ができて来院 というサイクルに入る子どもたちが一定数いるので
そのサイクルに入らないようにしてあげたいと思っていました
乳歯は 真ん中から ABCDEとよぶ歯で 5本 それが上下左右で20本あるのですが、
2歳でDを大きい虫歯にしてくる→治療する→3歳で2歳の時には生えてなかったEを虫歯にしてくる というサイクルのお子さんがいるのです。
これが一番予防したいパターンです。
それで 初診のとき、定期健診のときには、虫歯はどうしてなるのか?
予防するにはどうしたらよいか?
ということについてお話しています。
できることから 簡単に 取り入れてもらえればいいと思います。
歯が丈夫で長持ちすることは、健康に生きることにつながりますよ。
2018年3月5日 | カテゴリー:食育 |
こどもに 虫歯をつくらない 5つのポイント
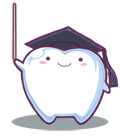
お子さんをできれば 虫歯で苦労しないようにしてあげたいと思いませんか?
それは難しいことだと思っていませんか。
でも・・・実は、そんなことないんですよ。
これだけ気をつけてくれれば 虫歯ゼロに育つ!という5つのポイントを紹介します。
ポイント1 3歳までできるだけ 砂糖の入った おやつを避ける!
歯が生えてから3歳までの間に 口の中に虫歯菌が住み着きます。
この期間に住み着いた虫歯菌の数が少なければ、虫歯になりにくい子供になります。
3歳まではできるだけ砂糖の入ったお菓子を与えるのを避けましょう。
当院では こどもたちを むし歯ゼロに育てることを目標とする歯科医院です。
もうすでに4歳になっているという方、まだ大丈夫です。
次から読んでみてください。
ポイント2
小学3年生まで 寝る前に1回、仕上げ磨きをする!
大人の歯の要、6歳臼歯は生えた直後から2年間が一番虫歯になりやすい時期です。
(だいたい年長から2年生までの間に生えます)
その時期までは必ず仕上げ磨きをしましょう。
ポイント3おやつの種類を選ぶ
ジュース(乳酸飲料、ポカリ等も含む)、飴、ひっつくおやつ(ハイチュー、キャラメル、ガム)は避けましょう。
果物やおにぎりなど、何日も保存がきかない食べ物のほうが虫歯になりにくいおやつです。
ポイント4 3度の食事以外に おやつは2回まで
ここでいうおやつには、ジュースを飲む、牛乳を飲む、ということも含みます。
だらだらと食べていると、お口の中のPHが下がった状態が続き、歯が溶け続けます。
規則正しい食生活で 歯を守りましょう。
ポイント5フッ素入りジェルを使用する
赤ちゃんのときから、うがいしなくても大丈夫な フッ素入りジェルを少し歯ブラシにつけて、仕上げ磨きをしてあげましょう。
歯質が強化されて、虫歯になりにくくなります。
上の5つで取り入れられるものがあったらぜひ1個でも2個でも取り入れてみてくださいね。
2018年1月29日 | カテゴリー:こどもの 口腔機能を 育てるには, 食育 |







