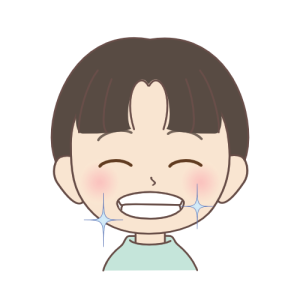結構よくある咬合性外傷🥶
さて、あまり聞き慣れない言葉が出てきました。『咬合性外傷』、一体何なのでしょうか(´ε`;)ウーン…。
外傷はわかりますよね。咬合は咬み合わせのことです。そうなると、『咬合性外傷』は、咬み合わせによって起こる外傷ということになります😊。そんなことがあるのか❓って思いますよね。でも、咬む力はかなり強いです。自分の体重以上の力がかなりの頻度でかかっています。この力によって、歯を支える歯ぐきや骨に影響がでてきた状態を『咬合性外傷』と呼んでいます🥶。
この、『咬合性外傷』ですが健康な歯ぐきや骨でも、歯周病が進んだ歯ぐきや骨でも起こりえます。要は歯を支える力以上の咬む力が加われば起こるのです😢。歯ぐきや骨がどんなに健康で強くても、咬む力の方が大きければ起こります。歯ぐきや骨が歯周病で弱っていても、咬む力が弱ければ起こりません。
私達歯医者さんが歯や歯ぐきに症状を訴えている患者さんを診る場合、最初に疑っているのは虫歯や歯周病です🦠。お口に中の2大疾患ですから当然ですね。しかし、虫歯や歯周病がない、歯も歯ぐきも特に問題が無いことも結構あります。そういった場合に、次に疑う病気の有力候補が『咬合性外傷』となります👍。でも、これがまた結構難しいのです😢。
『咬合性外傷』の代表的な症状を少しみてみましょう。「冷たいものや熱いものがしみる。」、「食べるときに痛い、変な感じがする。」、「ずきずき痛い。」などなど。うん、虫歯や歯周病でもみられる症状ですね。大体、患者さんも虫歯や歯周病なのだろうと思って来院されています。でも、見た感じは大丈夫なのです。私達歯医者さんとしては説明が難しい。厄介なことに、歯を支える力や咬む力は単純にみてわかるものではありません。パッと見てすぐに『咬合性外傷』だと言えるものではないのです😅。
それでもお口の中のいろいろなサインをみて判断していきます。そのサインもたくさんあります。例えば、、、、、
・歯の揺れ。
・歯の病的移動。
・骨隆起(咬む力に対抗して骨が厚くなります。)。
・舌や頬に歯型が付いている(咬み締めたりしている方に多いです。)。
・歯ぎしりや食いしばりがある。
・歯の咬耗、摩耗。
・歯の破折。
・銀歯や詰め物がはずれやすい。
・レントゲンで歯の根の周りの黒味が強い。
・レントゲンで歯の根の周りの骨の白味が強い。
などなど、、、、、😢。
たくさんありますね💦。しかもこれらの所見は他の病気でもみられるものであることに注意が必要です。咬合性外傷の治療としては、マウスピースを作ることもあれば、歯を削って咬み合わせの調整を行うこともあります🥶。本当に、『咬合性外傷』なのか慎重な判断が必要になるのです。
歯や歯ぐきに症状がでて、歯医者さんに行ったけど虫歯も歯周病もないと言われそのままにしている方は結構いらっしゃいます。そういった方は『咬合性外傷』の可能性があります。一度、全体的に詳しくみてもらうことをお勧めします。気になることがあればご相談くださいね。
2026年2月5日 | カテゴリー:新着情報, これがお薦め ホームケア, 歯科の豆知識 Q&A, 歯の外傷について, 歯を長持ちさせるには, 院長からの発信, 治療について |